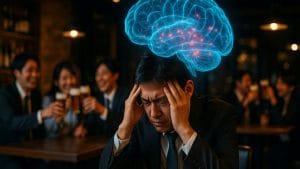こんにちは、渋谷のカフェバー「SPRING NOTE」でマスターをしている大塚です。
お店にいると、「お酒に強い女性の基準って何だろう?」という会話がよく聞こえてきます。
例えば、ビールやワインを何杯飲めたら「強い」のか、手軽な缶のチューハイやサワーならどうなのか、といった具合です。
また、「そもそも女性はお酒に強い体質なの?」という根本的な問いや、「男性との違い」、「お酒は何パーから強いと言える?」といった具体的な関心も多いようです。
さらには、自分が弱いかもしれないと感じた時の診断方法から、周りが酒豪だと思う女性の飲酒量はどれくらいなのか、そして健康を考えた女性の適正飲酒量は?まで、お酒の強さに関する話題は尽きません。
この記事では、長年たくさんのお客様と接してきたバーのマスターという視点から、そういった尽きない疑問について、一つひとつ紐解いていきます。
- お酒の強さを決定づける遺伝的・体質的な要因
- アルコールの分解能力における男女間の違い
- お酒の種類ごとの適正な飲酒量の具体的な目安
- 自身のアルコール耐性を手軽に知るための診断方法
お酒強い女性の基準と体質的な要因

- そもそも女性はお酒に強い?
- 男性とのアルコール分解能力の違い
- お酒に弱いか診断する方法とは
- ワイン好きに強い人が多い理由
- お酒は何パーから強いと言える?
そもそも女性はお酒に強い?

結論から言うと、一般的に女性は男性に比べてアルコールの影響を受けやすい体質です。
そのため、「お酒に強い女性」は相対的に少ない傾向にあると言えます。
その理由は、主に身体的な構造の違いにあります。
厚生労働省が運営する情報サイト「e-ヘルスネット」によると、女性が酔いやすい要因として以下の点が挙げられています。
- 体格と水分量
一般的に女性は男性より小柄で、体内の水分量が少ないです。アルコールは体内の水分に溶け込むため、水分量が少ないと同じ量のお酒を飲んでも血中アルコール濃度が高くなりやすくなります。 - アルコールの代謝能力
女性の肝臓は男性に比べて小さい傾向があり、アルコールの代謝能力が平均して男性の4分の3程度とされています。
このような理由から、女性は男性と同じペースで飲酒すると、急性アルコール中毒になるリスクが高まります。
もちろん個人差はありますが、性別による身体的な違いがアルコールへの耐性に大きく影響しているのです。
男性とのアルコール分解能力の違い

前述の通り、女性と男性ではアルコールの分解能力に差があります。
この違いをもう少し具体的に見ていきましょう。
アルコールは体内に入ると、主に肝臓で分解されます。
この分解プロセスには複数の酵素が関わりますが、その働きが男女で異なるのです。
男性に比べて女性は、アルコールを分解する酵素の働きが弱い傾向にあります。
このため、体重や飲酒量が同じであっても、女性の方が体内にアルコールが留まる時間が長くなり、血中アルコール濃度もより高い状態で推移します。
結果として、少ない飲酒量でも酔いやすく、酔いが醒めるのにも時間がかかるのです。
この分解能力の違いは、お酒の楽しみ方にも影響を与えます。
男性と同じ感覚で飲んでしまうと、意図せずとも飲み過ぎてしまい、二日酔いや健康への悪影響につながる可能性が高くなります。
お酒と上手に付き合うためには、この性差を理解しておくことが非常に大切です。
お酒に弱いか診断する方法とは

自分がアルコールに強い体質か弱い体質かを知ることは、健康的な飲酒のために重要です。
遺伝的な体質を手軽にチェックする方法として、「エタノールパッチテスト」があります。
これは、アルコールに対する皮膚の反応を見ることで、アルコール分解過程で生じる有害物質「アセトアルデヒド」を分解する酵素の活性度を推測する方法です。
エタノールパッチテストの簡単な手順
- 消毒用アルコール(エタノール濃度70%)を絆創膏のガーゼ部分に数滴染み込ませます。
- その絆創膏を、皮膚の柔らかい上腕の内側に貼り付けます。
- 7分後に絆創膏を剥がします。
- 剥がしてから10分後に、皮膚の色を確認します。
判定の目安
- 皮膚の色が変わらない
アセトアルデヒドを分解する酵素が正常に働く「お酒に強いタイプ(NN型)」の可能性が高いです。 - 皮膚が赤くなる
酵素の働きが全くない「お酒が飲めないタイプ(DD型)」の可能性があります。 - 最初は変化がなく、時間が経ってから赤くなる
酵素の働きが弱い「お酒に弱いタイプ(ND型)」の可能性があります。
ただし、このテストはあくまで簡易的な目安です。
より正確な体質を知りたい場合は、医療機関で遺伝子検査を受けることもできます。
自分の体質を把握し、無理のない飲酒を心がけましょう。
ワイン好きに強い人が多い理由

「ワイン好きの女性はお酒に強い」というイメージを持つ方がいるかもしれません。
これには、いくつかの理由が考えられます。
まず、ワインはビールなどと比較してアルコール度数が高い傾向にあるため、一杯をゆっくりと時間をかけて味わいながら飲むことが多いです。
この飲み方が、急激な血中アルコール濃度の上昇を抑え、結果として悪酔いしにくくさせている可能性があります。
また、日常的にワインを飲む文化のある国、例えばフランスの女性は、遺伝的にアルコール分解酵素の活性が高い人が多いという背景もあります。
もちろん日本人にも当てはまるわけではありませんが、文化的な飲酒習慣が耐性を高める一因となることも考えられます。
さらに、ワインは食事と一緒に楽しまれることがほとんどです。
食べ物、特に油分やたんぱく質を含む料理と一緒に摂ることで、アルコールの吸収が緩やかになります。
このように、ワイン特有の飲み方や食文化が、結果として「ワイン好きは強い」という印象につながっているのかもしれません。
お酒は何パーから強いと言える?

「アルコール度数が何パーセントからお酒に強いと言えるのか」という問いに対して、明確な基準は存在しません。
お酒の強さは度数だけで決まるのではなく、飲む人の体質や飲む量、ペースに大きく左右されるためです。
しかし、飲酒量の基準として、厚生労働省が推進する「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒」を1日平均の純アルコールで約20g程度と定義しています。
これは、アルコールによる健康リスクを抑える上での一つの目安です。
この純アルコール20gが、様々なお酒でどのくらいの量に相当するのかを見てみましょう。
| お酒の種類 | アルコール度数(目安) | 純アルコール20gに相当する量 |
|---|---|---|
| ビール | 5% | 中瓶1本(500ml) |
| 日本酒 | 15% | 1合(180ml) |
| ワイン | 12% | グラス2杯弱(約200ml) |
| 焼酎 | 25% | グラス半分(約100ml) |
| ウイスキー | 40% | ダブル1杯(60ml) |
| 缶チューハイ | 7% | 1缶(350ml) |
このように、度数が高いお酒ほど、少ない量で純アルコール20gに達します。
つまり、度数が高いお酒をたくさん飲める人が「強い」と見なされがちですが、健康の観点からは、度数に関わらず純アルコールの総量を意識することが重要です。

お酒強い基準になる女性の飲酒量を解説

- ビールは何杯からがお酒に強い?
- 缶1本あたりの純アルコール量
- チューハイとサワーの度数の違い
- 酒豪だと思う女性の飲酒量
- 健康的な女性の適正飲酒量は?
ビールは何杯からがお酒に強い?

ビールを基準にしてお酒の強さを考える方は多いでしょう。
では、ビールを何杯飲めたら「お酒に強い」と言えるのでしょうか。
前述の通り、厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は、純アルコール量で約20gです。
これは、アルコール度数5%のビールの場合、中瓶やロング缶(500ml)1本に相当します。
つまり、健康的な飲酒の観点からは、1日にロング缶1本が適量ということになります。
一方で、同じく厚生労働省は1日平均で純アルコール量60gを超える飲酒を「多量飲酒」と定義しています。
これはビールに換算すると、ロング缶(500ml)で3本分です。
このことから、毎日ビールを3本以上飲んでいる人は、飲酒量だけで見れば「お酒に強い」と言えるかもしれません。
しかし、これは同時に健康リスクを高める「多量飲酒者」の領域に入っていることも意味します。
杯数だけでなく、長期的な健康への影響も考慮することが大切です。
缶1本あたりの純アルコール量

手軽に楽しめる缶入りのお酒ですが、1本あたりにどれくらいの純アルコールが含まれているかご存知でしょうか。
純アルコール量は以下の計算式で算出できます。
飲んだ量(ml) × アルコール度数(%) / 100 × 0.8(アルコールの比重) = 純アルコール量(g)
この式を使って、代表的な缶入りのお酒の純アルコール量を計算してみましょう。
| 商品名(例) | 容量 | 度数 | 純アルコール量(約) |
|---|---|---|---|
| アサヒスーパードライ(アサヒビール) | 350ml | 5% | 14g |
| -196℃ ストロングゼロ(サントリー) | 350ml | 9% | 25.2g |
| 氷結® 無糖 レモン(キリン) | 350ml | 7% | 19.6g |
| 檸檬堂 定番レモン(コカ・コーラ) | 350ml | 5% | 14g |
※商品の成分や度数は変更される場合があります。
正確な情報は各公式サイトでご確認ください。
表を見ると、同じ350ml缶でも、アルコール度数によって純アルコール量が大きく異なることがわかります。
特にアルコール度数9%のストロング系チューハイは、1缶で「節度ある適度な飲酒」の目安である20gを超えてしまいます。
缶のお酒を選ぶ際は、度数を確認し、純アルコール量を意識することが健康的な飲酒につながります。
チューハイとサワーの度数の違い

チューハイとサワーは、どちらも焼酎などの蒸留酒をベースに、果汁や炭酸水で割ったお酒として広く親しまれています。
実は、この二つの間に厳密な定義上の違いはありません。
お店やメーカーによって呼び方が異なるのが実情です。
重要なのは、そのアルコール度数の幅広さです。
市場には、アルコール度数3%程度の飲みやすいものから、9%を超える「ストロング系」と呼ばれる高アルコールの商品まで、多種多様なチューハイやサワーが存在します。
特に注意したいのが、ストロング系の製品です。
ジュースのような飲みやすさから、アルコール度数の高さを意識せずに飲んでしまいがちですが、前述の通り350ml缶1本で純アルコール20gを軽々と超えてしまいます。
これは、お酒の強さを決める遺伝的要因の一つ、ALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)の働きが弱い日本人にとっては、特に負担が大きくなる可能性があります。
チューハイやサワーを選ぶ際は、単に味の好みだけでなく、必ずアルコール度数を確認し、自分の体質に合ったものを選ぶようにしましょう。

酒豪だと思う女性の飲酒量

「酒豪」という言葉に、明確な基準や定義はありません。
しかし一般的には、非常に多くのお酒を飲んでも顔色一つ変えず、酔った様子を見せない人を指すことが多いでしょう。
飲酒量の観点から一つの目安を考えるとすれば、厚生労働省が定義する「多量飲酒者」が参考になります。
これは、1日平均で純アルコールにして60g以上を摂取する人々のことです。
この純アルコール60gを、具体的なお酒の量に換算すると以下のようになります。
- ビール(5%)
ロング缶(500ml)3本 - 日本酒(15%)
3合 - ストロング系チューハイ(9%)
350ml缶 約2.7本
毎日これ以上の量を飲める女性は、間違いなく「酒豪」と呼ばれるでしょう。
しかし、これはアルコール耐性が高いというだけでなく、アルコール依存症や肝障害をはじめとする様々な健康リスクと隣り合わせの状態です。
お酒に強いことと、健康的に飲めることは同義ではない点を理解しておく必要があります。
健康的な女性の適正飲酒量は?

これまで見てきたように、女性は男性よりもアルコールの影響を受けやすいため、飲酒量の基準もより慎重に考える必要があります。
厚生労働省が示す1日あたりの純アルコール約20gという「節度ある適度な飲酒」の基準は、主にアルコール代謝能力が平均的な日本人男性を対象としています。
そのため、女性の場合は、その半分から3分の2程度、つまり純アルコール量で10g〜15gくらいがより安全な目安とされています。
この量を身近なお酒に換算すると、以下のようになります。
- ビール(5%)
レギュラー缶(350ml)1本弱 - ワイン(12%)
グラス1杯(約120ml) - 缶チューハイ(5%)
レギュラー缶(350ml)1本
また、量だけでなく、飲み方も重要です。
公益社団法人アルコール健康医学協会は「適正飲酒の10か条」の中で、週に2日は飲酒しない日、つまり「休肝日」を設けることを推奨しています。
肝臓を休ませることで、アルコールによる負担を軽減し、長く健康にお酒と付き合うことができます。
自分に合った健康的な飲酒習慣を心がけましょう。
まとめ:お酒強い女性の基準を知る

- お酒の強さは遺伝や体質で決まり明確な基準はない
- 女性は男性よりアルコールの影響を受けやすい
- 理由は体格、水分量、肝臓の代謝能力の違いによる
- 自分のアルコール耐性を知るにはパッチテストが手軽
- より正確な診断は医療機関での遺伝子検査で可能
- 度数が高いお酒を多く飲める人が強いと見なされがち
- 健康の指標は純アルコール量で考えることが重要
- 厚生労働省が示す男性の適正飲酒は純アルコール20g
- これはビール中瓶1本、日本酒1合に相当
- 女性の適正飲酒量は男性の半分から3分の2が目安
- 純アルコール量10gから15g程度を意識する
- ストロング系チューハイは1缶で適量を超えることも
- 多量飲酒の目安は純アルコール60g以上
- 酒豪と呼ばれる飲酒量は健康リスクと隣り合わせ
- 週に2日程度の休肝日を設けることが推奨される